

ドッグセラピストは、専門的に訓練されたセラピードッグと共に活動し、犬との触れ合いを通じて人々の心身の健康をサポートする専門家です。主な活動の対象は、高齢者、障がいを持つ方、病気の治療やリハビリテーションを受けている方、そして心にストレスを抱える子どもたちなど多岐にわたります。
犬が持つ人を癒やす力を介して、利用者の精神的な安定を促し、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上を目指す、社会的に大きな意義を持つ仕事です。
この仕事は、単に犬が好きという気持ちだけでは務まりません。まず、主役である犬の行動や心理を深く理解し、犬にストレスを与えずに能力を最大限に引き出すための知識と技術が不可欠です。
同時に、様々な背景を持つ利用者と円滑な関係を築くための高いコミュニケーション能力も求められます。予期せぬ事態にも冷静に対処できる忍耐力と観察力、そして何よりも、犬と人の両方に対する深い愛情と敬意を持っている人が、ドッグセラピストとして活躍できるでしょう。

ドッグセラピストの仕事は、犬を連れて施設を訪問するだけではありません。その活動は、計画、実践、犬のケアなど、多岐にわたる専門的な業務から成り立っています。
ドッグセラピストの活動は、主に「動物介在療法(AAT: Animal Assisted Therapy)」と「動物介在活動(AAA: Animal Assisted Activity)」の二つに分類されます。動物介在療法は、医師や作業療法士などの専門家と連携し、利用者のリハビリテーションなどを目的とした治療行為の一環として行われます。
一方、動物介在活動は、レクリエーションやQOLの向上を目的とした触れ合い活動を指します。高齢者施設で利用者の方々がトイ・プードルのような小型犬を撫でたり、抱っこしたりすることで、精神的な安らぎや会話のきっかけを生み出すのは、この活動の一例です。
活動を共にするセラピードッグの育成と管理も、ドッグセラピストの重要な仕事です。人懐っこく穏やかな性格であることはもちろん、様々な環境や刺激に動じない社会性を身につけさせるためのトレーニングを行います。
また、常に犬の健康状態に気を配り、ストレスのサインを見逃さないようにすることも不可欠です。犬が最高のコンディションで活動に臨めるよう、日々のケアを徹底することが求められます。

ドッグセラピストを目指すには、専門的な知識と技術を体系的に学ぶことが第一歩となります。確立されたルートは一つではありませんが、いくつかの代表的な道筋が存在します。
高校卒業後の進路として、動物系の専門学校や大学を選ぶ方法があります。
こうした学校では、「動物行動学」や「動物看護学」といった犬に関する専門知識に加え、「動物介在療法論」や「人と動物の関係学」など、ドッグセラピーに特化したカリキュラムを学べる場合があります。基礎から応用までを体系的に学べるため、着実に力をつけたい人に向いています。
社会人からのキャリアチェンジを目指す場合や、特定の技術を集中して学びたい場合は、民間の団体が運営する養成スクールや通信講座を利用する方法があります。働きながらでも自分のペースで学習を進められるのが利点です。
ただし、団体によって学べる内容やレベル、取得できる資格が異なるため、自分の目的に合ったスクールを慎重に選ぶ必要があります。
団体に所属せず、個人事業主として活動するドッグセラピストもいます。
この場合、セラピーの技術だけでなく、施設への営業活動、契約交渉、スケジュール管理、経理といった経営に関する知識も全て自分で担うことになります。安定した活動基盤を築くまでには困難も伴いますが、自分の理念に基づいた自由な活動ができるという魅力があります。

ドッグセラピストの専門性を活かせる職場は、徐々に広がりを見せています。ただし、常勤での雇用はまだ少なく、多くは非常勤や業務委託という形で活動しています。
病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障がい者支援施設などが主な活動の場となります。
ここでは、利用者の心身機能の維持・向上や、精神的な安定を目的としたセラピー活動を行います。常勤のドッグセラピストとして雇用されるケースは稀で、特定の曜日に訪問する非常勤職員や、イベントごとに依頼を受ける形で関わることが一般的です。
NPO法人や一般社団法人といった、ドッグセラピストの派遣を専門に行う団体に所属する方法もあります。団体が施設との契約やスケジュール調整を行うため、セラピストは活動そのものに集中しやすいという利点があります。
多くの場合、団体の認定資格を取得することが所属の条件となります。
小学校や特別支援学校などで、動物との正しい触れ合い方を教える「動物介在教育(AAE: Animal Assisted Education)」の一環として活動するケースもあります。子どもたちの情操教育や、命の大切さを学ぶ機会として、その役割が期待されています。

結論から言うと、ドッグセラピストとして活動するために法律で定められた必須の国家資格は存在しません。無資格であってもドッグセラピストを名乗り、活動すること自体は可能です。
しかし、専門的な知識や技術を持っていることを客観的に証明し、施設や利用者からの信頼を得るためには、民間資格の取得が極めて重要となります。
ドッグセラピーに関する民間資格は、様々なNPO法人や協会、民間のスクールが認定・発行しています。これらの資格を取得する過程で、動物行動学、人と動物の関係学、セラピーの具体的な技法、ハンドリング技術、関連法規などを体系的に学ぶことができます。
資格は、自身のスキルを証明し、就職や活動の機会を広げるための強力な武器となります。
ドッグセラピーの専門資格に加え、他の関連資格を併せ持つことで、活動の幅や専門性をさらに高めることができます。例えば、犬の飼育全般に関する知識を証明する「愛玩動物飼養管理士」や、セラピードッグのトレーニングに直接役立つ「ドッグトレーナー」関連の資格は非常に有用です。
また、福祉施設で活動する上では、「介護職員初任者研修」のような介護系の資格があると、利用者への理解が深まり、現場の職員との連携もスムーズになります。
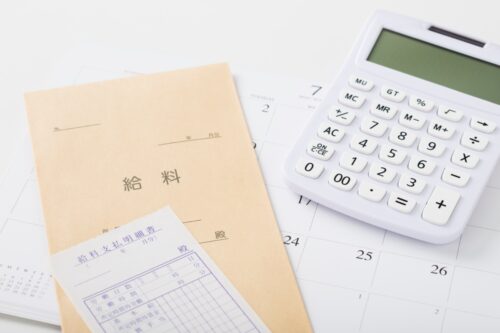
ドッグセラピストの給料は、その働き方や活動形態によって大きく異なり、現時点では専門職として安定した高収入を得るのは容易ではないのが実情です。
正社員としての求人が非常に少なく、多くが非常勤やボランティアとしての活動であるため、給与の相場を一概に示すことは困難ですが、参考としてペット業界全体の給与水準である年収250万円から400万円程度が一つの目安となります。
NPO法人などの派遣団体に所属する場合、給与や謝礼は団体の規定に準じますが、活動が非営利目的であることが多く、報酬は高くない傾向にあります。
フリーランスとして個人で活動する場合、1回の訪問あたりで報酬が支払われることが多く、料金設定は交渉次第ですが、安定した収入を得るには自身での営業努力が不可欠です。
動物病院やペットサロンが兼業としてサービスを提供している場合、その施設の給与体系に準じますが、ドッグセラピー専門の担当者としての給与というよりは、動物看護師やトリマーとしての給与がベースになることがほとんどです。
一般的に、高齢者施設や病院などの活動先が多い都市部では、ドッグセラピーの需要も高く、活動の機会を見つけやすい傾向にあります。それに伴い、報酬も地方よりは高い水準になる可能性があります。
一方、地方ではドッグセラピー自体の認知度がまだ低く、活動の場を開拓するところから始めなければならないケースも少なくありません。ただし、地域に根ざした活動で信頼を築くことができれば、唯一無二の存在として活躍できる可能性も秘めています。

ドッグセラピストは、犬と人との絆を通じて、多くの人々に癒やしと希望をもたらす、非常にやりがいの大きい職業です。高齢化が進む社会において、その役割は今後ますます重要になっていくことでしょう。
しかし、その一方で、専門職としての地位や収入がまだ安定しているとは言えず、職業として成立させるには多くの努力を要するのも事実です。ドッグセラピストを目指すには、「犬が好き」という純粋な気持ちを原動力としながらも、動物と人間の両方に関する深い知識、専門的な技術、そしてビジネスとしての視点を身につけることが不可欠です。
この記事で得た情報を参考に、ご自身のキャリアプランを現実的に見つめ、夢への一歩を踏み出してください。